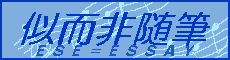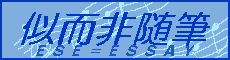ショパンvs.シューマンvs.リスト
1810年前後の数年間は、音楽史上奇跡的と言ってよいほどに大物が次々と誕生している。1685年のバッハ・ヘンデル・スカルラッティの3人同年生まれというのもすごいが、この時期、1809年にメンデルスゾーンが、1810年にショパンとシューマンが、1811年にリストが、そして1813年にヴァーグナーとヴェルディが生まれているのである。
この中で、ヴェルディはイタリアオペラの巨匠であって、他の連中とあまり接触があった形跡はない。強いて言えばドイツオペラの第一人者であったヴァーグナーに対して多少の対抗意識があったかもしれないが、他ならぬそのヴァーグナーがオペラというものに思想性などを付加することによって交響曲などの純音楽に匹敵し得るだけの内容を盛り込むまでは、オペラというのは現代の映画音楽などと同じで、もっぱら娯楽作品として理解されていた。そのため、ここに挙げた他の作曲家たちとは少々異質と考えなければならない。
ヴァーグナーはリストの娘のコジマと結婚したから当然リストと接触はあったが、ヴァーグナーのライバルとして面白い人物は他にいるので、ここでは触れない。
ともかく、ごく近接した時期に、これだけのそうそうたる大音楽家が輩出したのは他に例を見ない。中でも、ショパン・シューマン・リストの3人はお互い仲もよく、才能が磨き合ってそれぞれの輝きを増すことになったよい例として、しばしば取り上げられる。
注目すべきは、この3人はそれぞれ国籍を異にしているということだ。シューマンはドイツ人だが、ショパンはポーランド人、リストはハンガリー生まれである。もっとも、リストは生まれがハンガリーなだけで、マジャール人(ハンガリーの固有民族で、匈奴の末裔と言われる)の血は混ざっておらず、血統的にはドイツ人らしい。
この中で、最初に名が知られたのはリストである。彼は有名な練習曲作家でピアノの名教師であったカール・ツェルニー(1791-1857)の弟子であり、その引きで幼い頃からピアニストとして音楽界にデビューした。ツェルニーの先生であるベートーヴェンにもかわいがられたようだ。
13歳の時、作曲家で楽譜出版業者でもあったアントン・ディアベリ(1781-1858)が企画した、「50人の作曲家による変奏曲」に名前を連ね、これが作曲家としてのデビューになった。この変奏曲というのは、50人の作曲家にディアベリ自作のワルツの変奏をひとつずつ書いて貰い、ひとつのまとまった変奏曲にするというものだった。ディアベリはベートーヴェンにも参加を依頼したが、企画が遅々として進まないうちに、ベートーヴェンはひとりで33も変奏を書いてしまったので、ディアベリはやむを得ずこれを「第1部」として出版した。今に残るベートーヴェンのいわゆる「ディアベリ変奏曲」がこれである。
ショパンもやはり少年時代からその才能を属目されてはいたものの、なにぶんポーランドという、ヨーロッパの主要部から見るといささか辺境に近い国での活躍だったため、その声望が国際的になるのは少し遅れた。
シューマンはもともと趣味として音楽をやっていた人で、大学では法学を学んでいる。そして世に出たのは、音楽家としてより、音楽評論家としての方が早かった。彼の最初の出版された作品である「アベッグ変奏曲」と、最初の評論発表は同じ1831年に出ているが、作品の方で彼の名が知れ渡るのはもう少し後のことである。だが、評論の方はなかなか衝撃的で、21歳の青年論客の名を高めた。当時まだほとんど無名だったショパンの作品を論じ、
――諸君、脱帽したまえ。天才の出現だ!
と書いたのはこの論文である。ショパンが大いに力づけられたのは言うまでもない。
ショパンはその当時、パリに居たが、そこでリストに出逢った。リストは大変親切に、このぽっと出の若者の面倒を見たようである。1歳下とはいえ、すでにヨーロッパ中で有名だったリストとの友誼は、ショパンにとって大変ありがたいものだった。ショパンは感謝の気持ちを込めて、「別れの曲」「黒鍵のエチュード」「革命のエチュード」など有名な作品を含む練習曲集op.10をリストに献呈している。また、リストはのちに、ジョルジュ・サンドをショパンに紹介している。言うまでもなく、ショパンの後半生を彩る女流詩人である。
ショパンとシューマンが実際に顔を合わせたのは1835年夏のことであるが、シューマンはすでに「謝肉祭」の中で「ショパン」というタイトルの楽章を書いていた。この「謝肉祭」はピアノによる連作短編小説集といったおもむきの作品で、ダヴィッド同盟という架空の組織が登場し、音楽上の保守反動勢力に対して戦いを挑み、勝利する、という、かなり稚気をおびた設定がなされている。同盟のメンバーにはシューマンが同志と認めた人々が加えられていて、ショパンもそのひとりと見なされたわけである。
ショパンと実際に会ったシューマンは、意欲作「クライスレリアーナ」op.16を献呈した。ショパンの方はこれに応えて、バラード第2番op.38をシューマンに贈った。
シューマンとリストが直接に接したのはいつからかわからないが、リストがベートーヴェン没後10周年を記念して記念碑を建造しようとした時、シューマンは、この作品による利益を基金に廻して欲しいと、幻想曲op.17をリストに献呈したので、その頃からかもしれない。ただしリストがこれに応えたのは15年近くあとのことで、シューマンが精神分裂症を発病する直前に、リストのただ一曲のピアノソナタを献呈している。
このように、曲を贈ったり贈られたり、親密な仲を感じさせ、しかもそれぞれにお互いから大きな影響を受けつつ、独自の世界を育んで行った。才能のあり方として、理想的な形がここにあるような気がする。
ヴァーグナーvs.ハンスリック
今までの項目では、作曲家同士のライバル関係を扱ってきた。まだこの時代、作曲家と演奏家ははっきりとは分化していなかったということもある。演奏家を兼ねないプロパーな作曲家で、はじめて名が知られるのは、多分無理な練習のし過ぎで指を傷め、ピアニストへの道を断念したシューマンからではないかと思う。
一方、作曲家を兼ねないプロパーな演奏畑の最初の大物は、リストの娘コジマと最初に結婚したハンス・フォン・ビューロー(1830-1894)ではないかと思う。彼はピアニストで名指揮者だったが、特に作曲はしていない。
さらに、「音楽評論家」として最初に現れるのはエドゥアルト・ハンスリック(1825-1904)と言ってよい。シューマンも最初は評論家としてデビューしたわけだが、のち大作曲家に名を連ねた。ハンスリックは作曲もせず、演奏活動もしなかった。音楽評論で一本立ちしたのは、少なくとも名が知られている人物としては彼が最初である。
ハンスリックは最初リストやヴァーグナーの音楽に心酔したが、のちにそれらの作品を排斥するようになる。上記のリストのピアノソナタを、支離滅裂で芸術の名に価しないと一蹴したりしたのだが、彼が生涯の敵としたのは誰よりもヴァーグナーであった。ヴァーグナーの作品や、それに影響を受けた後進の作曲家たちの作品をこっぴどく批判し続けたのである。有名なところでは、チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を聴いて、
――臭い匂いがする。
と酷評したという話がある。
――ヴァーグナーは音楽芸術の敵である。
と言い放ち、その作品は音楽を無理矢理言葉に隷属させた不自然な表現で、人声の生理をまったく無視した旋律線、オーケストラの誇大な響きで肉声を押しつぶし、あらゆる様式美を破壊しようという暴挙である、と、これでもかとばかりに書き綴った。
彼の論拠は要するに、音楽はそれ自体が完結された芸術であって、他の表現に従属させられるべきものではないという点にある。19世紀には、いわゆる標題音楽が流行して、文学作品や美術作品を音で表現するという試みが、いささか安易に行われていた。ハンスリックはそれが我慢ならなかったのである。
音楽にはおのずから備わった形式美というものがあり、形式美をきわめてこそ音楽としての価値が高まるというのが彼の持論だった。彼は形式美を無視あるいは破壊したあらゆる試みに反対した。
しかし、時代の流れはやはり、古典的な形式を破壊する方向へと動いていた。むしろ人々のエトスが、古典的な形式感の中ではとても表現しきれないほどに複雑・巨大なものになりつつあったと言うべきかもしれない。
彼の奮闘にもかかわらず、社会はヴァーグナー的な行き方を許容し始めた。大きな流れの中で、ハンスリックの立場が保守反動そのものになって行ったのもやむを得ない。
ハンスリックは一念発起して、代表作「音楽美論」を書き上げた。この長編評論はそれなりに影響力があり、やはり音楽はそれ自体の純粋性を保つべきではないかという議論はその後長く続いたのである。
さて、標的にされたヴァーグナーがまた、評論家などに叩かれて黙っているようなおとなしい男ではない。彼は文学的才能もなかなかのもので、オペラや楽劇の台本はほとんど自分自身で書いている。バイロイトという小さな寒村の議会を口車に乗せて、、自分の作品のみのための劇場を建てさせるほどの口のうまさも持っている。彼はハンスリックの攻撃に堂々反論し、その偏狭な反動的言辞を逆に攻撃した。
ヴァーグナーの強みは、彼が実作者であった点であろう。彼は、いささか子供じみた意趣返しさえ作品の中で行っている。彼の代表的な楽劇のひとつである「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の中に出てくる、ドジばかり踏む敵役のベックメッサーという登場人物が、実はハンスリックをモデルにしたものなのである。何せ第1稿ではこの人物はハンス・リッヒなる名前になっていて、
――君、それはあんまりだろう。
と友人たちに諫められて名前を変えたのだという。
ハンスリックはどうあがいても、自分自身の作品で持論を立証するということができない。そこで、自陣営の旗頭に、ブラームスを担ぎ出した。確かにブラームスは古典的な形式美を重んじた作曲家であり、標題音楽と呼べるような作品はほとんど書いていない。ハンスリックはブラームスを徹底的にヨイショし、これこそ音楽であると褒めちぎった。
それがブラームスにとって幸福であったかどうかはわからない。純粋音楽の旗手として担がれてしまったがゆえに、自由な発想を妨げられてしまったのかもしれないのである。ブラームス自身は、ヴァーグナーとは違う行き方であったとはいえ、この先輩を素直に尊敬していたようだ。晩年の作品には、和声の使い方など、ヴァーグナーからの影響もかなり顕著に見られるのである。むしろハンスリックの押し掛け女房的なヨイショを、有難迷惑に感じていたかもしれない。
ハンスリックはその毒舌で多くの敵を作ったが、憎まれっ子世にはばかるというのはまさに彼のためにあるような言葉で、音楽家たちの憎しみを買いつつ79歳の長寿を保った。彼が死んだ1904年には、宿敵ヴァーグナー、旗頭として担いだブラームスはもちろんのこと、ヴァーグナー亡きあとその衣鉢を継いだブルックナーも、臭い匂いをまき散らした(?)チャイコフスキーも、とうにこの世の人ではなかった。少なくとも長寿合戦では、70歳で亡くなったヴァーグナーには大差で勝ったわけである。
(1998.5.11.)
|