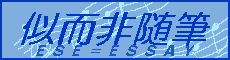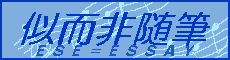|
「レコードなんて代物はね君、あれはウンコみたいなものだよ」
学生の時、ピアノを習っていた先生が、ある時そんなことを言った。
私のプロフィールには先生の名前がたいてい載るから、実名を隠しても仕方がない。「題名のない音楽会」などにしばしば出演しているピアニストの神野明である。
私が2年生の時に芸大の非常勤講師となられて、その年の副科ピアノのクラス分けで先生のクラスとなり、以後卒業まで3年間ピアノを師事しただけでなく、その後もかなり親しくおつき合いいただいている。
師事したと言っても、副科のレッスンなど週に20分ほどのもので、しかも休暇のやたら多い学校ではあり、そんなにみっちり教えられたというわけでもない。その3年間で私のピアノがどれくらい上達したかもわれながら定かでなく、正面切って神野明の弟子ですと名乗ることには少々気後れを覚えなくもない。
しかし、常に日本中から招聘を受けて忙しく飛び回り、演奏をしたことのない都道府県はほとんどないというほどの現役バリバリの先生について、現場からの感触というものを問わず語りにお聞きすることができたのは、私の幸せであったと思っている。
最初のレッスンの時、先生は私に、
「君は、ひとつの曲をじっくり仕上げるのが好きかね、それともいろんな曲に手をつけるのが好きかね」
と訊ねられた。
のっけからこんな質問をするピアノの先生は珍しい。1年生の時に習っていた先生(この人も大変高名なピアニストであったが)は、ひとつの曲にかかると何ヶ月もそればかり続けたのである。私は飽きっぽいたちなのでいい加減うんざりした。それだけじっくりと1曲を叩き込まれたわりに、試験の成績はかなり不本意なものであった。
そんな経験もあるし、私は昔から、いろんな曲、できるだけ知らない曲を弾くのが好きで、受験までついていた先生から与えられる課題曲とは別に、楽譜屋へ行っては妙な楽譜を買ってきては勝手に弾いていた。おかげで課題曲の練習はすっかりおろそかになるのが常であった。
だから私は迷わず、
「いろんな曲に手をつけるのが好きです」
と答えた。
神野先生は、うなづいて言った。
「じゃあ、そういう方針で行くとしよう」
それから3年間、試験のために学校から課される課題曲は別として、私は実にいろんな曲をレッスンに持って行った。
この曲は先生も知らないだろう、と思われるようなのを探し出しては練習して、持ってゆくのである。中には中国の作曲家の作品なんてのもあった。3年生の時に中国旅行をしたので、その旅先で買ってきた楽譜だったのである。
先生の方も面白がって、たまに知っている曲だったりすると、
「お、これなら知ってるぞ」
と、得意そうに言われた。
知られていないわけではないが、まあ普通の人はあんまり弾かない、ショパンの第1番のソナタとか、ベートーヴェンの2つの前奏曲などもレッスンして貰った。
たいてい2週間くらいで1曲を上げていたようだ。最初の週に私が弾いて、アドヴァイスを貰い、それを念頭に置いて翌週もう一度弾き、それでおしまいということが多かった。演奏技術を深めるという点では甚だ不徹底なレッスンではあったが、何やらゲームをやっているようでもあり、練習にも身が入ったのは事実である。
実際の話、あれほどじっくり同じ曲を弾き込まされた1年生の時の試験より、先生にレッスンを受け始めた2年生以降の試験の方が、成績も上がっていたのだった。
先生の演奏について私が批評がましいことを言うような立場にはないが、正確な演奏という点では、どうかと思うことがないでもない。演奏会を聴きに行っても、時折
──あれ?
と首を傾げることがある。具体例は憚るが、曲の一部を不本意的にカットなさったこともあれば、左手がすっかり真っ白になっておられたこともあるのである。ミスタッチも決して少なくはない。
が、そういう瑕瑾を超えて、なんだかわからないが納得させられてしまうところが先生の演奏の真骨頂らしい。説得力のある演奏、ということの大事さを学ばせて貰っている。
演奏会場というのは、言うまでもなく舞台・演奏家と客席・聴衆とのコミュニケーションの場である。
歌い手などはそのことをよくわかっている人が多いが、ピアニストとなると、客席が直接視界に入らない横向きの体勢で演奏するせいか、ともすれば客の存在を忘れた演奏になりがちである。少なくとも、自分がピアノを弾いているというそのことが、客席との対話なのだということを明確に意識している人はそう多くない。
神野先生は、そのあたりをとても大事になさっているのである。
曲の「決め」のような部分で、からだをどちらへ向けるかなどということまで計算している。計算と言うよりも本能と言うべきことかもしれない。客席に背中を向けるような静止の仕方をするべきではないと、レッスンでも言われたことがある。
演奏会とは、ただ演奏者の発する音を聴くだけの場ではない。演奏者の動きを見、息づかいを感じることにより、客席も共にひとつのフィールドを形作ってゆくべき相互作用の場なのだ。
ツィメルマンのリサイタルを聴いた時に、一流の演奏家というのは客席の呼吸を支配できるものなのだなと感心したことがあるが、逆に言えば客席の呼吸を感じてそれに応えてゆくというのも、演奏家の大切な心得に違いない。
とにかく、舞台の上下が一体となって一晩の感動を作って行くのが演奏会なのであって、そういう意味ではどれほど時が経っても、科学力が進んでも、ナマの演奏会というものが廃れることはあり得まいし、その感動が薄れるということもあり得ないだろうと私は考えている。
「レコードなんて代物はね君、あれはウンコみたいなものだよ」
冒頭に書いたこのセリフは、そういう演奏の場で活躍し続けておられる先生にとってみれば、当然の感慨であっただろう。
世のオーディオマニアが激怒しそうな言葉ではあるし、私もはじめてその言葉を聞いたときは唖然として、
「はあ……ウンコ……ですか……?」
と問い返したものだったが、先生の言わんとすることはよくわかるような気がした。
先生にとっては、会場に集まった聴客たちとの一期一会の出逢い、彼らと共に作った何時間かの感動の共有が大切なのであって、それを録音するなどということは余分のことであり、録音の結果できてきたレコード(CD)などというものは、いちばん大切な部分を切り捨てた、まさに排泄物のようなものに過ぎないのである。
確かに、上に書いたような
──あれ?
と思ってしまった演奏を、もし録音してあとで聴けば、そこばかりがひどく気になって、いちばん大事な演奏の説得力の部分が感じられなくなるだろうということは容易に想像がつく。
現場で活動している音楽家には、意外とオーディオマニアがいない。というより両者は全く重ならないのではないかと思うくらいである。
「オーディオのことはよくわかんないや。CDなんか自分がやるための参考程度に聴くだけだし」
という人が多く、私もまったくその通りである。現場の人間には、レコード=排泄物という考え方が、多かれ少なかれ共通してあるように思われる。
学校を卒業してから、先生に技術的指導を受けることはなくなったが、音楽家としてもっと大切なことをいろいろと教わっている。本当はそういうところにこそレッスン料を払うべきなのだが、しばしば酒の席であるとか、先生と私が共に関係している音楽団体の親睦旅行の席であるとか、そうした場で語られるさまざまなことに、学ぶことは多いのである。
神野明の今年のリサイタルは、9月10日(金)午後7時から、四谷の紀尾井ホールで開催される。今年(1999)はショパンの没後150年ということで、ショパンの作品を大体年代順に並べたプログラムとなっている。間もなくであり、楽しみにしている。
(1999.9.1.)
|