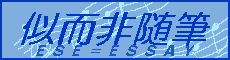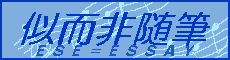|
そもそも「クラシック音楽」とはなんぞや、ということを説明する時、私はよく、ヨハン・シュトラウス父子(父1804〜49、子1825〜99)を例に引く。
父は「ワルツの父」、子は「ワルツ王」と呼ばれ、19世紀ヨーロッパの台風の目であったウイーンにおいて、一世を風靡した作曲家父子。ショパンが反撥し、ブラームスが憧れ、オッフェンバック、レハール、ワルトトイフェルなど数多くの追随者を出し、今なお彼らのウインナ・ワルツの愛好者は後を絶たない、堂々たるクラシック音楽の巨匠である。
だが、ここで考えなければならないのは、当時彼らの音楽がどう理解されていたかということだ。ワルツというと、優雅、洗練、古典的というような形容が浮かんで来るのだが、その頃の上・中流階級の紳士淑女がつどってワルツを踊った「舞踏会」とは、現代に喩えるなら何に当たるのかを考えてみよう。
その答えは意外と簡単にわかる。「舞踏会」をそのまま英語にしてみればよろしい。
もちろん「ダンス・パーティ」となるはずである。
これを略した「ダンパ」が、現代の若者にとってどういうイメージの言葉であるかを考えれば、19世紀の、鹿鳴館的華麗さに彩られた「舞踏会」がどういうものであったのか、大体想像はつくであろう。
そう、ディスコだったのである。
当時のヨーロッパは、ナポレオン戦争後の混乱が、深刻に跡を引いていた。特にウイーンは辣腕家メッテルニヒの反動政治下にあり、その頽廃、目を覆うばかりだったのは映画「会議は踊る」の示す通りである。こういう社会で、若者が鬱屈するのは今も昔も変わりはない。そこで金のある連中は、夜な夜な最新ファッションに身を包み、ひと夜のアヴァンチュールを求めて社交場に通いつめる。金とファッションセンスのある者しか入れないのは、現代の高級ディスコと全く同様。
そこには、女をナンパすることしか考えていない不良紳士や、男あさりに精を出す貴婦人、すなわちジゴロや高級娼婦があふれ返っていたのは、オペラ「椿姫」に描かれている通り。彼らの服装も、現代の眼で見れば古風で優雅だが、当時の年寄りには眉をひそめさせる、19世紀版イケイケ・ファッションだったのである。そこでは、あやしげな麻薬や媚薬を売りさばくブローカーもいたことだろうし、まあ現代の盛り場とちっとも変わらない。
「舞踏会」がディスコであったならば、そこで演奏されたウインナ・ワルツは、ディスコ音楽であったとしか言いようがない。つまり現代で言うならヘヴィメタであったり、フュージョンであったり、ソウルであったり、要するに軽音楽なのだ。
ただ、当時はまだ録音技術というものがなかったから、舞踏会が開かれるたびに、生演奏する楽団が雇われた。そのあたりは確かに豪勢なものである。ヨハン・シュトラウスは父子とも、自分の楽団を率いて、毎晩のようにあちこちの舞踏会を渡り歩いた。いわばディスクジョッキーであり、ディレクターであり、さらにアーティストでさえあったのだから、彼らがウイーン社交界の寵児となったのは当然であろう。
ヨハン・シュトラウスのワルツは大抵、パートナーに申し込むための導入部があり、趣きの違う4、5曲のワルツが連続し、最後に大きく盛り上がって終わるという形をとる。これは明らかに、実用音楽ならではの配慮だ。
彼らは自分の名前がクラシック音楽史に残るとは全く考えていなかったろう。
しかし、いい物は残る。
それが深刻な苦悩の産物であろうが、金のために書きとばした代物であろうが、関係はない。それが非情にして面白い「時代」の作用である。「時代」のふるいにかけられて残った物だけが「クラシック」の栄誉ある称号を受けるのだ。
逆に言えば、どの音楽が「クラシック」になるのかは、同時代の人間には絶対に、原理的にわからない。百年後の世界で、20世紀のクラシック音楽として何が数えられているか、興味深いものがある。
なお、「ワルツ王」は百四十数曲のワルツの他、ポルカやオペレッタなど、実に500曲を超える作品を書いているが、現在演奏されるのは、その5パーセントにも満たない20曲程度に過ぎないということも、書き添えておこう。
|