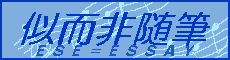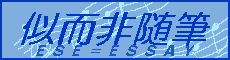|
「白鳥の歌」といえば言うまでもなくシューベルトの最後の歌曲集だが、実はシューベルト自身が歌曲集としてまとめたものではない。彼が最晩年に書いた「レルシュタープとハイネの詩による13の歌曲」に、出版人のハスリンガーが絶筆である「鳩の便り」を加えて一冊にまとめ、『白鳥の歌』というタイトルをつけたのであった。ハスリンガーとしては、「13の歌」の終曲である「影法師」(実に暗い曲である)でシューベルト最後の歌曲集を締めくくるのでは、あまりに救いがないと考えたらしい。
いずれにしろ、「13の歌」の中にも、そのものずばりの「白鳥の歌」という曲はない。このタイトルはハスリンガーが自分の創意でつけたのである。
実を言うと、「白鳥の歌」というのは、ヨーロッパでは「いまわの際の言葉」という意味で使われる言葉なのである。白鳥はアヒルとは違って滅多に啼き声を立てない。ただ生命の火が燃え尽きる直前にだけ、哀切な、美しい啼き声を長々と奏でる。本当にそうなのかどうか私は知らないが、とにかくヨーロッパ人はそう考えているらしい。古いマドリガルなどにも、白鳥が死に瀕して啼くといった内容の歌が少なくない。
人の死なんとするその言やよし、というところかもしれない。白鳥の断末魔の叫びから転じて、人の最後の言葉、あるいは作品、を意味するようになった。
作曲家の最後の作品というのは、こちらがそのつもりで聴くせいもあるかもしれないが、どこかせつない印象がある。
はやばやと筆を折ってしまったロッシーニとか、事故などの被害者となって、本人の思いもよらない形で生を終えたグラナドス(第一次世界大戦中に乗っていた船が撃沈され死亡)やヴェーベルン(第二次世界大戦直後の深夜、家の外に出てタバコを吸っていたら、銃火と誤認した進駐軍の米兵に射殺された)は別として、自分の死期というのはだいたいわかるものなのかもしれない、最後の作品には、間近の死を予感させるようなものが少なくない。
それが30代で若死にしようが、80代まで生きていようが、同様であるのが、なんとも不思議な気がする。
J.S.バッハの晩年は、彼の愛した荘厳なポリフォニー音楽(複数のメロディーを組み合わせることで構成される音楽)の体系が崩れ始め、ロココ風な、単純で軽いホモフォニー音楽(「メロディーと伴奏」による音楽)が好まれていた。バッハが生涯をかけて作り続けたフーガなどはすでに時代遅れとなりつつあったのだ。
バッハは新しい風潮の到来を、哀しみをもって眺めていたのだろうが、生涯の最後の10年に至って、自分のやってきたことの総決算をするつもりになったのかもしれない。一種カタログ的な作品を次々と手がける。まずは1741年に発表された「ゴールドベルク変奏曲」で、これは当時の鍵盤音楽のありとあらゆるスタイルを網羅的に示した作品である。
1747年には「音楽の捧げもの」を発表。前項にも書いたが、カノンという形式の集大成と言ってよい。また、リチェルカーレ、トリオソナタといった、やはり当時としてはすでに下火になっていた形式も採り入れている。
そしてそれと並行して、死の直前まで書き続けられたのが「フーガの技法」だ。こちらはタイトル通り、フーガという形式に用いられる各種の技法のカタログになっている。明らかにバッハはライフワークのつもりでこれを書いており、かつて毎週一曲ずつのカンタータを書き飛ばしていた速筆ぶりに似合わず、何度も何度も推敲し書き直した形跡がある。
この作品をどういう形で演奏すべきかという問題はかなり議論になっているが、私の見るところ、バッハ自身、具体的な楽器のことなどすでに突き抜けてしまっているように感じられる。実際のところ、この作品はどんな楽器で演奏してもどこかに無理が生ずる。無理が生じないのは強いて言えば声楽アンサンブルくらいかもしれない。バッハはクラヴィーア曲、室内楽曲、あるいは管弦楽曲という具体物を書いたつもりはなく、あくまで抽象化された「フーガ」を書いたのに違いない。
ほとんど鬼気迫るような執念を感じる作品集だが、バッハは「フーガの技法」を完成させることができなかった。最後の大フーガに、自分の名前B-A-C-Hによる主題を導入し、いよいよこれから盛り上がるというところで絶筆となったのである。なんだか巨匠の心残りがその辺に漂っているようで、不気味でさえある。
ヘンデルはバッハと同年に生まれ、9年長生きしたが、最後の手稿譜は1751年のオラトリオ「イェフタ」に53年に加筆した部分とされている。68歳のヘンデルは緑内障にかかっており、ほぼ失明していた。現代なら点字譜タイプライターがあるが、当時はまだそんなものはなく、自ら筆をふるうことはできなくなってしまった。
だが、その後も57年にオラトリオ「時と真理の勝利」が発表された。これは大部分が、20年前の同名の作品と共通しているものだが、わずかながらオリジナルの部分も含まれている。弟子に口述筆記させたらしい。一応これが、ヘンデルの最後の作品とされている。
2年後、ヘンデルはこの世を去った。74歳である。当時としては長命であった。
モーツァルトの絶筆は有名なレクイエムである。この第7曲「ラクリモーザ」の8小節目まで書いたところでモーツァルトは息絶えた。ただ、少々ややこしいのだが、これに続く第8曲と第9曲はほとんど完成しており、オーケストレイションを仕上げさえすればよい状態になっていた。1曲目から順番に作曲していたわけではないらしい。
レクイエムは、灰色のコートを着た謎の男によって委嘱された、という。この謎の男というのは、シュトッパッハ伯爵なる貴族の使いの者に過ぎなかったのだが、モーツァルトはこの委嘱主の正体を知らなかったらしい。そのためか、不摂生と妙な薬でいい加減ガタガタになっていたモーツァルトは、この使いの男を死神のように思い、レクイエムも自分の葬式のために書いているような気がしていたという。これはモーツァルト自身が友人への手紙に書いているから本当だろう。シュトッパッハ伯爵というのは、あちこちの作曲家に曲を書かせて、自分の作品としてサロンで発表するのを趣味にしていた男である。現代から見るとけしからぬ話だが、当時はそんなこともよくあったようだ。
モーツァルトがレクイエムを仕上げられずに死んでしまったので、弟子のズュスマイヤーがあとを補作して完成させた。ズュスマイヤーはこの補作によってのみ後世に知られており、自分の作品というものもあったと思われるがほとんど残っていない。レクイエムの中で、第10曲「サンクトゥス」と第11曲「ベネディクトゥス」はズュスマイヤーのオリジナルだ。
彼の補作については毀誉褒貶いろいろあるが、まあかなり立派にやっているとは思う。
モーツァルトにしてはオーケストラが重すぎるのではないかという意見は根強く唱えられているが、正真正銘モーツァルト自身が完成させた第1曲からして、彼のそれまでの作品に較べると結構オーケストレイションが重い。やはり自らの死を前にした沈鬱な気分というものが感じられるのである。間違いなく死を予測した音楽だという気がする。
ハイドンはモーツァルトよりずっと長生きした。生まれたのは24年前だが、死んだのは18年後である。
ハイドンの「白鳥の歌」はあまりはっきりしない。というのは、彼は1802年でほぼ作曲活動から足を洗っているからである。1809年まで生きたのだから、晩年の作品にもさほど死の影のようなものは感じられない。
一応最後の作品とされているのは作品103の弦楽四重奏曲だが、これは未完である。未完といっても、完成させる時間がハイドンに残されていなかったというのではなく、シューベルトの「未完成」同様、単に放置されただけであるようだ。
サリエリなども、ハイドンと同じ頃に筆を断っているが、いわゆる古典派音楽にどっぷり浸かっていた彼らとしては、当時の新潮流であるロマン主義傾向に我慢がならなかったのだろう。
古典派とロマン派の差異については、第17回で詳述した。普遍のベクトルを持ち、全世界へ向かって自分の歌を歌うことのできた古典時代から、よりナショナリスティック乃至ドメスティックなベクトルを持つようになるロマン派時代への移行については、フランス革命とそれに続くナポレオン戦争の影響が大きいと考えられる。ベートーヴェンすらもこの時期大いに惑い悩んだ形跡があるのだから、より古典派的であったハイドンやサリエリが、自分の信じる音楽が時代に適わなくなったことを感じて、作曲の意欲を失ってしまったことは、驚くにはあたらない。この時代の価値観の変化、古典派とロマン派の違いというのは、これで見るとわれわれが想像する以上のものがあったように思えるのである。
ベートーヴェンは面白いことに、どのジャンルの作品でも、その最後のものは不思議な予感に満ちている。
ベートーヴェンの死因は肝臓病だったと考えられるが、彼は残された時間を悟っていたようだ。最後の数年に書かれた作品は、ほとんどどれもが、「これが最後」と意識されたような作品になっているのだ。
交響曲第9番はもちろんそれまでの交響曲の概念を一変させる歴史的作品であるが、ベートーヴェンは次の第10番にもとりかかってはいた。しかし、自分の手でそれを完成させられないことはわかっていたのではないかと思えてならない。「第九」のあとに何をすべきだったのか、自分でもよくわからなかったのではなかろうか。
最後のピアノソナタ第32番は、「第九」に先んずること2年、1822年に作られているが、そのラストは限りなく天国的に静謐で、この作品が絶筆だったと言われても充分納得できる。ピアノ曲ではそのあと「ディアベリ変奏曲」やバガテルなどが書かれている。最後のバガテル(作品126)など、どこか謎めいた印象さえ与えられる。
実際の「白鳥の歌」となったのは弦楽四重奏曲だった。1826年、第16番(作品135)が完成された。晩年のベートーヴェンは弦楽四重奏に凝っていたようで、ほとんどつづけざまに5つも仕上げている。この最後の第16番となると、さすがに精気の衰えのようなものが感じられないでもない。
なお、同じく弦楽四重奏曲第13番(作品130)の終楽章として初稿で書かれたのがいわゆる「弦楽四重奏のための大フーガ」で、これはのちに加筆した上で独立の作品(作品133)として発表された。そのため、終楽章がなくなってしまった第13番には、のちに別のフィナーレが付け加えられた。もしかすると、この新しいフィナーレの方が第16番より後に書いた可能性もある。いずれにしてもベートーヴェンは弦楽四重奏によって筆を絶ったことになる。
幸い、未完で、執念を残しながら死んだと思われる曲はなかったようだ。交響曲第10番の断片は、スケッチ程度であって、まだ手をつけたとも言えないような状態であった。
なお、ベートーヴェンほどの偉人になると、本当の「いまわの際の言葉」も記録されている。
──友よ喝采せよ、喜劇は終わった。
というのだ。これはヘンデルの「メサイア」の歌詞からの引用であるが、実際には死の3日前に、若い友人のシンドラー(のちにベートーヴェンの伝記を書いた)らに向かって言った言葉だ。
まるで自分の生涯を痛烈に笑い飛ばすかのような、大楽聖にふさわしい最期の言葉に見えるが、この言葉を発したのはそれほど深刻な背景があったわけではない。
実は、この言葉を発する直前、彼は遺言状に署名していたのである。ベートーヴェンはこの時すでにもうよろよろで、ペンも満足に使えなくなっていた。ぶるぶると震える手を抑えながら、長い時間をかけてようやく署名し終わったので、傍らにいた友人たちに向かい、照れ隠しのように上記の言葉を言ったのだった。つまり「喜劇」というのは、人生などという深い意味はなく、単に覚束ない手つきで署名したことを指すに過ぎない。
似たような話として、ゲーテが死ぬ前に
──もっと光を。
と言ったというのも、別に
「世の中を覆っているこの無知蒙昧の霧を吹き払いたまえ」
などという意味はまったくなく、ただ死ぬ前の視野狭窄で視界が暗くなったから、
「明かりをつけてくれ」
と言っただけの話だという。
偉い人というのは死ぬ前に何かカッコいいことを言うことになっているようだが、たとえ誰かの創作ではなくても、こんな風に後世が勝手に深読みしている場合が多いようである。
だとすると、「白鳥の歌」になんらかの意味を見出そうというのも、さほど意義のある詮索とは言えないかもしれない。
とはいえ、「書く」という作業は単に「話す」のとは違って、当人の意識がより強く反映されると思いたい。絶筆を探るのは、やはり彼らが最期を前にして何を思ったかということを想像するよすがとなるのではないだろうか。
そんなわけで、この項、次回に続きます。 (2000.7.8..) |