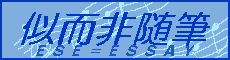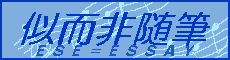|
ブラームスの音楽的な軌跡というのは、かなりわかりやすい。古典主義者であるとか形式主義者であるとか言われているが、それは非常に一面的な見方であると思う。実際には、ブラームスほどにその時々の精神状態や思索内容が作品から汲み取りやすい作曲家は珍しいほどだ。彼は文学的業績によって博士号(Ph.D.)を持っていたくらいだから、自己の状態を明晰に把握する能力がすぐれていたのだろう。そしてそれをしっかり作品に反映させている。
彼は確かにあからさまな標題音楽はほとんど書いていないし、オペラなども遺さなかったが、それだからと言って彼が反ロマン主義的であったと判断するのは早計だろう。個人の思索遍歴を作品として定着させていったという点では、ブラームスはまごうことなきロマン派なのである。
晩年に近づくに従って、ブラームスの作品のそういった傾向はいよいよ強まる。
ブラームスの作品は、ほぼ作曲年代と作品番号が一致している(初期には多少混乱があるが)のでわかりやすいが、作品番号が3桁の大台に乗ってからの曲は、まさに晩年の悲哀といった雰囲気に満ちている。
その代表例が、作品116から119へと続く一連のピアノ小品だ。何曲かハイテンポで派手なものも含まれていて、演奏会などではそういうものの方が好まれているが、むしろゆっくりした地味なタイプの曲にこそ、ブラームスの孤独感、諦念、寂寥感といった気分が、極度に雄弁な説得力をもって込められていると私は思う。
私は「好きな作曲家」を問われてブラームスを挙げることはまずないけれど、気分が滅入った時など、これらの小品をピアノで弾いてみることが多い。なんだか知らないがいちいち琴線に響き、
──うん、うん、そうだよなあ。
などとうなづきたくなっている自分に気づく。
最後のピアノ小品である作品119の4「ラプソディ」ののち、彼は1894年に2曲のクラリネットソナタ(作品120)を書き、さらに1896年には歌曲の名作「バスのための4つの厳粛な歌」(作品121)を書いた。この歌曲のテキストはルター訳聖書によっていて、内容的にも最期を前にしての祈りという印象がある。暗く重々しい歌だが、「バスのための」歌曲というのは珍しいためもあってか、演奏される機会が多い。
そして、本当に最後になったのが同年のオルガンのための『11のコラール・プレリュード』(作品122)だった。その第11番、すなわち本当の本当の最後の作品のタイトルが「ああ世よ、私は去らねばならない」であったというのは、出来過ぎているようだが、ブラームスは死期を悟っていて自覚的に狙ったのに違いない。
渋すぎて理解されにくいが、実はブラームスという男はけっこうユーモア感覚があったらしい。自分を一生懸命ヨイショしてくれている評論家のハンスリックに、わざわざウインナ・ワルツ(作品39の「ワルツ集」)を書いて贈っているなどというのは、シャレのわかる人間でないとできることではない。ハンスリックは一貫して、音楽が軽薄華美に流れる傾向を憂慮し、確乎とした古典的形式の継承を唱えていた評論家であり、一方ウインナ・ワルツというのは当時としては軽薄華美の代表みたいなものであった。
そんなブラームスが、自分の最後の作品として「ああ世よ、私は去らねばならない」などというタイトルを選んだというのは、彼一流の渋いユーモア感覚からだったと考えても、それほど見当はずれではあるまいと思う。彼の死因は肝臓ガンであった。たぶん死期を予測するのは容易だったであろう。
ブラームス同様渋い作風で知られるフランス(生まれはベルギー)の作曲家フランクの最後の作品もまたオルガン曲(「3つのコラール」)である。フランクはオルガニストとして生涯を過ごした人だったから、この選択は自然と言えよう。
オルガニストとしては能力を認められていたものの、フランクは作曲家としては長いこと啼かず飛ばずだった。フランスの音楽潮流からすると、やはりドイツ的に渋すぎたと言える。
本人も模索を続けていた感じだったが、60歳を越えた途端、天の啓示を受けでもしたかのように、続々と名作を産み始める。彼の代表的な作品は、ほぼ最後の6年間ほどに集中しているのだ。具体的に言うと、
・死の6年前の1884年には,、フーガという古い形式に新境地をもたらしたピアノ曲「プレリュード、コラール、フーガ」が、
・85年には、これまた変奏曲という形式概念を一変させた、ピアノと管弦楽のための「交響的変奏曲」が、
・86年には、不朽の名作ヴァイオリンソナタが、
・87年には、ヴァイオリンソナタ同様「主題循環」技法に冴えを見せるピアノ曲「プレリュード、アリア、フィナーレ」が、
・88年には、それらを綜合した大作・ニ短調交響曲が、
・89年には、この初演でようやく人々がフランクの真価を理解したと言われるニ長調弦楽四重奏曲が……と、連年歴史的傑作を産みだし続け、そして死の年(90年)に至るのである。
このような傑作群で円熟した筆力を自分のものにしたフランクが、最後に生涯愛したオルガンのためにコラールを書いたのは自然な成り行きであろう。それだけに、この3曲のコラールは小品ながら、フランクの精髄のすべてが凝縮されて詰まっているように感じられる。その中でも最後の第3番は、オルガン音楽史上屈指の名作として、頻繁に愛奏されているのである。
チャイコフスキーの最後の作品はお馴染み交響曲第6番「悲愴」で、彼はこの作品の初演後間もなく死亡した。これもあまりにはまり過ぎていると思う人が多いかもしれない。この曲の、通例を無視したスローテンポな終楽章の、悲痛ともなんとも曰く言いがたいすすり泣くような曲想は、死を予感していると言われればあまりにもそれらし過ぎて、かえっていかがわしさを感じさせるようでさえある。
このシリーズの最初の回で述べたことに通じるが、どうも後世の人々はチャイコフスキーのエンターテイナー性を見落としがちであるように思う。彼の作品に、ブラームスのような感情や思索の直接の影響を求めすぎるのは危険ではあるまいか。
彼が泣かせを入れたいと思えば、どのようにでも泣かせるフレーズを書くことができたはずである。私には「悲愴」もそういう「コンセプト」によって書かれた曲であるように思う。悲愴というタイトル自体も、彼自身が考案したのではなく、マネージャー役だった弟のモデストの薦めでつけられたのだった。
「ペーチャ兄さん、今度の交響曲なんだが、今までの交響曲と違って、終楽章のテンポが遅くて曲想も暗いよね。この辺をうまくアピールするサブタイトルが欲しい気がするね」
「それもそうだなあ。どんなのがいいだろう」
「そうだね、『悲劇的(トラジディクスカヤ)』なんてのはどうかな」
「『悲劇的』ねえ。なんだかあざといような気がするが……」
「そうか……それなら、『悲愴(パテティクスカヤ)』はどうだ?」
「おお、そいつは洒落ている。そいつで行こう」
どうやら、このような会話が交わされたらしい。
チャイコフスキーは同じ年(1893年)にけっこう沢山曲を書いているが、必ずしも死を予感した暗い曲ばかりというわけではない。むしろピアノのための「18の小品」などに見られるように、あいかわらずド派手で楽観的な作品であることの方が多い。
チャイコフスキーの死因はコレラ説が定説となっていたが、「新グローブ音楽事典」では、甥ボブとのホモ関係の暴露をおそれて、自ら砒素をあおったのだと断言している。
コレラは伝染病であり、自殺にしてもこれは衝動的な感じであり、そんなに前から死が予想できたとは考えられない。チャイコフスキーが死の何ヶ月も前に、手間のかかる交響曲を最後の作品にしようとしたという考え方はどうも成り立たない気がする。
むしろ、「悲愴」が期せずして最後の作品となってしまったことに、われわれは運命というものの皮肉を感じるべきなのかもしれない。
ブルックナーの作曲活動は事実上40歳近くなってから始められている。若い頃にもハ長調ミサ曲やニ短調レクイエムなどのかなり大規模な作品が書かれているものの、全く指導を受けずにいわば独習で書いたものだけに、その後の交響曲などに比較するべくもない。
彼は72歳まで生きたので、作曲家としての活動期間は三十数年ということになる。5歳から活躍し、35歳で死んだモーツァルトも活動期間は30年だったことを考えると、何やら不思議な気がする。また、晩熟としか言いようがないブルックナーの存在は、われわれを大いに力づけてくれるものがある。
そのブルックナーの最後の作品は、未完に終わった交響曲第9番で、偶然か意図的か、ベートーヴェンと同じニ短調をとっている。
彼は旧作であっても、思い立つと徹底的に改訂したくなるたちだったらしく、大規模な作品でこの種の改訂がなされていないものはほとんどないほどである。9番が未完に終わったのも、旧作の改訂に時間をとられてしまったためとも言われている。なんとか第三楽章までは仕上げたものの、終楽章に手をつけることはできなかった。もっとも、この第三楽章には「生への別れ」の気分が反映されていると言われ、ここまでで終わってもそれなりに納得できる曲にはなっている。
なお、完成された曲で最後のものは、1893年に作曲された、男声合唱と管弦楽のための「ヘルゴラント」であった。
ベートーヴェン、ブルックナー、それにドヴォルザークもそうだったし、当時はシューベルトもそう思われていた……9番目の交響曲を書くとじきに作曲家は死ぬ。
このジンクスを異様なまでに気にしたのがマーラーである。これについては前に書いたが、もう一度触れてみよう。
1906年、46歳のマーラーは交響曲第8番(千人の交響曲)を完成させた。交響曲と言うよりはオラトリオと呼んだ方がふさわしい、8人の独唱者と大合唱を伴う大作である。実際、彼の交響曲は従来の交響曲の理論──たとえばソナタ形式といった──で分析するよりも、オペラとかオラトリオの立場から考えた方がわかりやすいところがある。ヴァーグナーはオペラに交響曲の原理を持ち込んだのだが、それをもう一度交響曲に応用したのがマーラーだと考えればよい。
それはともかく、このほとんど極限的なまでに巨大な交響曲を仕上げてのち、マーラーは
──次で終わりだ……
という意識を強く感じたらしい。
まだ40代半ばの彼にしてはいやに神経質になったものだが、翌07年には長女をジフテリアで失って、また自分自身にも心臓疾患が発見される。マーラーは恐怖に蒼ざめたことであろう。
08年に書いた「大地の歌」は、李白や孟浩然らの詩のドイツ語訳をテキストとしたもので、カンタータと呼べないことはないが、8番を交響曲と呼ぶくらいなら「大地の歌」の方がよほど交響曲らしい体裁を調えており、どう考えても交響曲第9番と呼ばれるべき作品だったが、マーラーはかたくなにこれを9番と呼ぶことを拒んだ。
それでなんとか死なずに済んだので、マーラーはひとまず安心して次の交響曲の作曲にとりかかる。だが、まだなんとなく不安だったのか、2曲を同時に進行させ始めたのだった。これなら9番と10番をほぼ同時に仕上げることができ、9番のジンクスを破れると思ったのであろう。そして、ジンクスさえ破ればもっと長生きができるという気がしていたのかもしれない。
だが、運命は皮肉だった。同時進行していた2曲のうち、ニ長調の交響曲が先にできたのだったが、もう一曲の嬰ヘ長調が仕上がる前に、彼の生命は尽きてしまったのである。それも、心配していた心臓病のためではなく、咽喉炎から併発した敗血症が原因だった。
当然ながら、人々はニ長調交響曲を第9番と呼び、嬰ヘ長調交響曲は「未完の第10番」と呼ぶことになった。やはりマーラーは、あれほど気にしていたジンクスを破ることができず、9番まで書いたところで力尽きてしまったのであった。
「大地の歌」を素直に9番と呼んでおけばジンクスは破れたのである。マーラーはみずから墓穴を掘ってしまったのだった。
(2000.8.1.) |