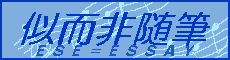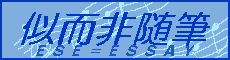|
不思議な章題だと思われるかもしれない。
ショパン(1810〜1849)はロマン派の旗手的存在であり、古典派音楽の象徴のようなソナタ形式とはあまり関係がなさそうに考えられている。
言うまでもなくソナタ形式というのは、前古典派〜古典派初期に活躍したバッハの息子たち──フリードリヒ、エマニュエル、クリスティアンなどなど──あたりによって確立され、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの古典派三大巨匠の手によって発展・完成を見た、音楽構造のひとつである。
今までこの雑文のシリーズでは、形式の説明などはあまりやってこなかったので、この機会にちょっとだけおさらいしておこう。
およそ効果的な表現というものは、対照性と統一感とを共に満たしていなければならない。例えば絵画であれば、光と陰の対照をどのように描くかで出来が決まると言ってよいが、かと言って中心素材だけ光の当て方が違うようではちぐはぐになる。そこにはおのずから全体の統一感というものが要求される。文芸作品の場合にはもっとわかりやすい。起承転結と言うが、転(対照的な部分)を経て結(しめくくり)に持ってゆくからこそ興味が持続できる。だらだらと一本道だけの作品など誰も読みたくはない。
対照性ばかり考えて統一感をおろそかにすれば支離滅裂になり、逆に統一感を図りすぎて途中の変化がなくなれば退屈になる。
ラヴェルのボレロなど、変化のない一本道ではないかと思われるかもしれないが、あれは対照性を音色の変化というただ一点に絞り込んで成功した例である。普通はもう少しいろんな要素(例えばメロディー、調性、リズムなど)によって対照を図るものだが、ラヴェルはあえて一点集中をやってのけたわけで、それができたのは「オーケストラの魔術師」の異名をとる彼の卓越したオーケストレイション能力があったればこそである。そんじょそこらの作曲家が真似しても失敗するのは眼に見えている。
よくできた曲には必ず対照性と統一感が鮮やかに決まっているものであり、これはどんなに短い曲でも言えることだ。例えばわずか8小節でできている唱歌「春が来た」などを考えてみるとよい。
最初の小節で「春が来た」と歌うが、次の小節はほぼ同じ形でやはり「春が来た」と繰り返す。これによってこの曲の冒頭のモティーフが強く印象づけられる。その次の2小節を使って「どこに来た」と歌うところは、メロディーラインの上でも、リズムの上でも、最初の2小節とは大きく異なり、鮮やかな対照を見せている。後半の「山に来た 里に来た 野にも来た」は、前半のリズムをそのまま継承しつつ、メロディーライン的には前半が下がってゆく傾向だったのと対照的に、ラストへ向かってぐいぐいと高まってゆくのである。このように、このすこぶる短い唱歌にも、見事な対照と統一がとられていることがわかる。
8小節というのは音楽を形作る最小のまとまりであると考えられる。これより短い曲がないわけではないが、どこか省略されているような印象を与えられる。ひとつの過不足ないまとまりとしては8小節くらいが妥当で、これを大楽節と呼んでいる。大楽節というからには小楽節というのもあるわけだが、今はそちらには踏み込まない。この大楽節ひとつだけで構成される曲──上記の「春が来た」あるいは「春よ来い」とか「赤とんぼ」とか──を学問的には一部形式という。
このまとまりが2つのものを二部形式、3つのものを三部形式というわけだが、そのまま四部形式、五部形式と増えてゆくのかと言えばそうではなく、三部形式で終わりである。なぜなら、4部分以上になれば、大楽節よりさらに大きなスケールでのまとまりが発生すると考えられるからである。つまり、全体が大きく2部分もしくは3部分に分かれ、その大きな部分がさらに2つなり3つなりに分けられる、という構造になることがほとんどで、こういう大きなものは複合二部形式もしくは複合三部形式と称される。
三部形式(あるいは複合三部形式)になると、まず主要なフレーズを置き、それに対して相当に対照的な中間部を置き、そのあとで最初の主要フレーズを繰り返すという、サンドイッチのような構造が取れるので、いろいろ応用が利く。対照的な部分を2つ以上置いて、その都度主要フレーズを繰り返すビッグマックみたいな構造も考えられ、これをロンド形式と呼ぶ。ロンドーという昔の舞曲が、リフレイン部分を蜿蜒繰り返しながら、なかば即興的に別のメロディー(ステップも)がはさまれてゆく形だったのでこの名がつけられたようだ。
このように音楽の形式というのは、どんな構造にすれば対照性と統一性を共に図れるかという探究から次第に確立されてきたのである。
その頂点と言うべきものが、ソナタ形式なのだ。
ロンド形式までは、ある程度自然発生的な構造であるが、ソナタ形式は明らかに思弁の成果である。例えば即興演奏でソナタ形式を作るのは相当に至難の業だ。楽譜というものが単なる心覚えでなく、作曲家の思索対象となる時代になってはじめて確立されたのだと考えてよい。
これは私一個の意見であり、音楽学界一般に認められているわけではないが、ソナタ形式には弁証法哲学の影があると思う。ベートーヴェンとヘーゲルが同い年(1770年生まれ)であったことは必ずしも偶然と言いきれないものがある。弁証法はむろんヘーゲルが発明したものではなく、彼が完成させたと考えるべきで、そういう哲学が完成されるような時代的気分というものが、18世紀という時期にあったことは間違いない。私が言いたいのは、そうした時代的気分が、一方ではソナタ形式を産み、一方ではヘーゲル哲学を産んだということなのだ。
弁証法におけるテーゼ──アンチテーゼ──その葛藤──止揚(アウフヘーベン)という推論過程は、そのままソナタ形式の第一主題──第二主題──展開部──再現部という構造原理に比較できる。
ソナタ形式では、きわめて対照的な2つの主題が置かれる。3つ以上に見えることもあるが、中心となるのは結局そのうち2つだということが多い。この両主題はいわば光と影であり、水と油であり、テーゼとアンチテーゼである。あらゆる点で対照的であるべきで、例えば「運命」の両主題などはその対照が際立っている。かたやハ短調、8分音符のせわしない同音連打と強烈なブレイクをもつ、不安で熱情的な第一主題。かたや変ホ長調、4分音符のなだらかなメロディーが波打つように連なる、居心地よく幸福な第二主題。
この対立を、こうした哲学的意味合いまで高めたのはまぎれもなくベートーヴェンであるが、彼に先行する音楽家たちも、両主題の存在が対照性のはっきりした表現であることはわかっていた。
全体の約3分の1ほどを占める主題呈示部(単に呈示部とも言う)の中に、このふたつの主題が置かれ、次の展開部では両主題がさまざまな形でもつれ合う。両主題から抽出された多くの要素が、あるいは調性を変え、あるいは音価を変えながらめまぐるしく展開されてゆく。実はこの部分こそ作曲家の腕の見せ所で、ソナタという形式がその後も多くの作曲家に好まれたのも、展開部があるからだったと言ってよい。
そして再現部である。私はこの部分をむしろ「止揚部」と呼びたいと思っている。弁証法におけるアウフヘーベンは、矛盾を内包させつつより高次の段階でそれを超克させるわけだが、ソナタ形式の再現部はまさにその意味でアウフヘーベンそのものなのだ。再び主題がもとの形で登場するのだが、第一主題と第二主題の対立はそのままで、古典的音楽ではもっとも重要な要素である調性という点において、両主題は統一される。呈示部の第二主題は原則として、長調の曲であれば属調(#のひとつ多いあるいは♭のひとつ少ない調。例えばト長調に対するニ長調)、短調の曲であれば並行調(#や♭の数が等しい長調。例えばニ短調に対するヘ長調)に置かれることが多い(この調関係には例外も多いが、別の調をとるという点は動かない)のだが、再現部ではこれが主調(短調の場合は同主調──主音を同じくする、例えばハ短調とハ長調のような関係──のこともある)で現れるのである。
呈示部とは両主題の調関係が異なるので、当然そのつなぎの部分(推移)も違った形になるわけで、ここもまた作曲家の腕の見せ所のひとつである。
対立する曲想を持つ主題の併置、その有機的展開といった、高度に知的な作業が必要とされるのがソナタ形式なのだ。ちなみに、これをソナタ形式と呼ぶのは、ソナタという多楽章構造の第一楽章に置かれることが多かったためである。もともと、いろんな性格を持つ器楽曲を数曲まとめた組曲をソナタと言ったが、バロック時代後期にはいわゆるバロック・ソナタとしていくぶん定型化し、また一方ではスカルラッティのソナタのように単楽章のものもあったが、18世紀半ばにはほぼ現在の形に落ち着いた。同じ頃さまざまな編成も整理され、現在では独奏楽器のためのソナタをソナタと呼び、独奏楽器とオーケストラによるものを協奏曲、オーケストラによるものを交響曲、数人のアンサンブルによるものを室内楽曲(「弦楽四重奏曲」など)と呼び分けている。
ソナタ形式にしろソナタにしろ、18世紀以降はこうした構造類型の呼称となったのである。
ベートーヴェンはソナタ形式の完成者であり、今なお最大の巨星である。彼の32曲のピアノソナタは、ソナタ形式という一定の構造類型のもとでどれほど多彩な音楽が作りうるかというカタログと言ってもよいくらいだ。ベートーヴェン以後、ソナタ形式に多少の変形を加えたり改造を試みたりした人はいたが、その構造に本質的な寄与をした作曲家はただのひとりもいない。ベートーヴェンと言えばソナタ形式、ソナタ形式と言えばベートーヴェンなのである。
さて、ようやくショパンの登場である。
ショパンの作風はこういう哲学的構築性、有機的展開などとは無縁だと思われている。一瞬のひらめきがもたらした美しいメロディー、即興的なパッセージ、斬新な和声などが彼の持ち味であり、主題を綿密に分析してその素材を組み合わせ、がっちりとした構造的な音楽を作ってゆくというベートーヴェン的資質の持ち主ではないと考えられてきた。
そういうショパンも、ピアノソナタを3曲と、ピアノ協奏曲を2曲(イ長調の第3番も書こうとしたが挫折)書いている。あと若い頃にピアノトリオト短調、晩年にチェロソナタト短調を書いているが、これらはさしあたって考えなくてもよかろう。
これらの解説などを読むと、一様に有機的展開の弱さに触れ、
──ショパンにとってソナタ形式の構築性は肌に合わず、むしろ苦痛でしかなかったと思われる。
などと書いてあることが多い。
本当にそうだろうか。2曲の協奏曲と第1番のソナタは、確かにごく若い頃の作品であり、一種の習作と見られないこともない。だが、ソナタ第2番変ロ短調(「葬送」)は中期の1839年(29歳)に、第3番ロ短調は後期のもっとも円熟しきった1844年(34歳)に書かれている。本当に苦痛でしかなかったのなら、こんなに各時期しっかり試みることはなかったのではないか。
ショパンはむしろ、ベートーヴェン的な構築性を、例えばシューベルトのようにそのまま真似しようとするのではなく、自分の資質に適った形で身につけたいといつも念じていたのではなかろうか。
作曲年代から言うと最初になるソナタ第1番ハ短調(作品4)は18歳の時の作品である。
私は一時期この曲をけっこう練習したが、まあ確かに習作的作品であることは否めない。表現が非常に冗長かつ饒舌であり、構成にも配慮が乏しい。
第一楽章はソナタ形式を目指したことは間違いないものの、調構造などがいい加減で、結果的には似て非なるものになってしまっている。諸井三郎氏は大著「楽式の研究」の中で、この第一楽章をソナタ形式とは認めていない。諸井先生が「明確にソナタ形式をとっている」と認めたのは終楽章だが、こちらもロンド形式と規定する人が時折いるくらい曖昧で、私の見るところあまり明確とは言えない。
この曲だけ見れば、ショパンがソナタ形式を苦手としたという通説も納得できる。
しかし考えてみれば、18歳と言えば、現代の音大作曲科の受験生(現役生)と同じ年齢である。彼らに「確乎とした構成感、有機的な展開」など求めてもなかなか困難なのではないか。私も受験前にソナタ形式の曲をむやみとたくさん作らされたが、もちろん習作の域を出るものではない。なんとなく決められた形にあてはめたというだけの話である。
それを思えば、若いショパンに過重な要求をするのは酷ではないかという気もする。構造上の難点はあるが、このソナタにはのちの作品に継承されてゆく原型的なアイディアがいろいろ含まれているし、特に第三楽章など5拍子という、その当時としてはおそろしく斬新なことをやっている。
要するにこの曲は習作なのであって、その証拠にショパンは生前この曲を出版していない。出版されたのは死後の1851年である。
第1番のソナタでいろいろ反省するところもあったのだろう、翌年から書き始められたピアノ協奏曲第2番ヘ短調(作品21)、さらにその翌年に書いた協奏曲第1番ホ短調(作品11──番号は出版順で、実際の作曲順は逆)と見てゆくと、ショパンが勉強していることが実によくわかる。
最初の練習曲集(作品10)と時期的に並行しており、ピアノの書法も見る見るうちに整理されてきていることが窺える。いずれも難曲ではあるが、ソナタ第1番、協奏曲第2番、協奏曲第1番と並べた場合、弾きやすさという点ではこの逆順になる。だんだん易しくなるという意味ではなく、ピアノという楽器を弾く時の指の生理に逆らわなくなってきているということだ。もちろん曲としての完成度はどんどん上がっている。
協奏曲第1番は、ピアノ協奏曲史上の傑作のひとつに数えられているが、なおオーケストレイションの未熟さなどが指摘されることが多い。これも実際には二十歳の青年としては無理からぬところで、オーケストレイションというのはある意味職人芸であり、場数がものを言うという面がかなり大きい。そんなに天才的なひらめきがなくとも、何曲何十曲と手がけているうちに手馴れてくるものだ。むしろ4曲も交響曲を書きながら最後まで一向に手馴れなかったシューマンの不器用さは特筆されてよい。
年齢と経験を考えれば、ショパンのオーケストレイション技術とて立派なものであるし、そういう条件を考えないとしても、不快な音がするとか野暮ったいとかそういうわけではなく、単にオーケストラが伴奏に徹していてあまりオーケストラとして活躍しないというだけの話で、それをあげつらってこの曲の欠点のように言うのは、半ばオタッキーな議論と言ってよい。
さて、ソナタ第2番(作品35)はホ短調協奏曲から9年後に書かれている。この間彼は社交界の寵児として、演奏に作曲に、レッスンに人づき合いに、おそろしく多忙な日々を送っていた。ショパンは意外にもマンガを描くのが得意で、漫談の名手でもあってまわりの人を常に爆笑させていた。そういう明るい才気にあふれていたばかりか美男子でもあったから、社交界のご婦人方がチヤホヤするのは当然であった。リストやシューマンといった有力な友人にも恵まれ、まさに順風満帆といったところである。
彼の生命を39歳で奪うことになる肺結核は、どうもこの時期、若さと健康に任せてむちゃくちゃな生活を続けていたツケとして忍び入ったものらしい。何しろ平均睡眠時間が3時間に満たなかったというような証言もあるくらいである。ジョルジュ・サンドとデキたのは1837年頃のことらしいが、ふたりで出かけたマジョルカ島の気候が決定的にショパンの健康を損ない、翌38年には大喀血をしている。ソナタ第2番はその後、ノアーンにあるサンドの自宅に移って小康状態になった時に書いた作品である。
いわば、自分の寿命に不安を抱いた時期に、あえてソナタという大きなものを手がけたというのは、やはり、
──おれは小曲だけの作曲家じゃないぞ。
ということを世に知らしめたいという気持ちがあったに違いないと私は思う。
もっとも、出来上がったソナタ第2番は、ソナタというより幻想小曲集の趣きがあるものになってしまった。
それぞれの楽章はよく吟味され、充分に聴き応えのあるまとまったものになっているし、その配列もあたかも「生と死の闘争──断末魔──葬式──墓場」というような一連のストーリーを思わせる構成になっている。第三楽章は有名な葬送行進曲であり、終楽章は絶え間なくユニゾンの走句が駆け回る非常に特異な音楽(おそらく前奏曲集第14番で試みた趣向を拡大したのだろう)である。大変独創的であることに疑いはない。
が、全体を通して聴いた場合、どうも音楽としての方向性が各楽章バラバラで、バランスを欠いて感じられるのも事実だ。
シューマンはこの曲を評して、
「これを『ソナタ』と呼ぶのは酔狂でないにしても気まぐれと呼ぶべきだろう」
と言っている。シューマンであればたぶん各楽章にタイトルをつけて、全体としてはそれこそ幻想小曲集といったタイトルで発表したのではないかと思われる。ソナタという呼称にこだわりさえしなければ、この曲は文句ない名曲なのだが。
そういうことは作曲者自身が実はいちばんよくわかっていただろうと想像する。
彼はそのあと、矢継ぎ早に大曲を作り始めるのだ。
スケルツォ第3番嬰ハ短調(作品39)と第4番ホ長調(作品54)、バラード第3番変イ長調(作品47)と第4番ヘ短調(作品52)、ポロネーズ第5番嬰ヘ短調(作品44)と第6番変イ長調(英雄ポロネーズ、作品53)、ワルツ第5番変イ長調(作品42)、幻想曲ヘ短調(作品49)……いずれも雄大な構想と巨匠的な表現力を備えた大曲である。ノクターンやマズルカでも、この時期にはそれまでのものと段違いの規模と構成力を備えた作品が作られている。
特にスケルツォとバラード、それに幻想曲が注目に価する。スケルツォ第3番ははっきりとソナタ形式を備えた力強い作品だ。むしろ優美というべき第4番は形式こそ三部形式であるが、その中に含まれるモティーフの有機的展開の作法は天才的なものがある。バラードはどちらも独特の変形を施されたソナタ形式で、ことに第4番の両主題の鮮やかな対照と、それが後半に至って渾然一体に融合されてゆくありさまはまさにベートーヴェンの最円熟期を髣髴とさせるものがある。幻想曲は、一見バラバラに見えるいろんな素材を実に要領よくまとめ上げた作品で、ソナタ形式とは言い切れないけれども、主題展開という点では見事の一語に尽きる。
こういった作品群で、いわば修行を積んだショパンは、第2番から5年経った1844年、ついに第3番のソナタ(作品58)を書くのである。満を持してという表現がぴったりではあるまいか。ソナタ形式に苦痛を感じていたどころか、実はソナタを書きたくて仕方がなかったのだと考えた方が正しいような気がする。
演奏所要時間は第1番よりむしろ短い。が、はるかに雄渾で大規模な印象を受ける。やはりここまで来るには17年の円熟が必要だったのだ。
まあ、第一楽章などは満を持し過ぎて、いささか素材が多すぎるきらいはある。ベートーヴェンやブラームスならこの第一楽章に含まれる素材だけで3曲くらいソナタを書いたかもしれない。次から次へとめまぐるしく新しいモティーフが導入されて、熱帯のジャングルのごとき様相を呈していないでもない。また、再現部で第一主題の再現を欠いているが、これは第2番のとりたてて工夫もない自己模倣であり、この曲の性格からすれば、繁殖しすぎたような展開部のあとで、高らかに第一主題が再帰していればもっと感動的だったろうとの評もある。がともあれ、楽章が終わったあとの充足感とすがすがしさは比類のないものがある。
私の見るところ、第三楽章もちょっと狙い過ぎかなという観がある。左手のリズム系が、ピアノで弾くとどことなくユーモラスな雰囲気になりがちなのだが、それはどうもショパンの本意ではなかったような気がするのだ。おそらく弦のピチカートなどでこの伴奏形を演奏すればはるかに効果的だろうし、右手に現れるメロディーも、木管楽器に似つかわしい。ショパンとしては実に珍しいことだが、あまりピアノ的発想の曲ではなく、むしろオーケストラ曲にふさわしい発想で書かれているように思う。
しかしそのあとの終楽章の素晴らしさの前に、そんな不満も吹き飛ぶ。余計な枝葉を一切取り払ったABABAの単純なロンド形式を用いながら、よくこれだけ聴く者を最後までぐいぐいと引っ張ってゆくことができるものだと感心する。
ショパンはこのソナタを書いたあと4年あまり生きるが、このあとの大曲と言えば舟唄嬰ヘ長調(作品60)と幻想ポロネーズ(作品61)があるくらいだ。
ソナタ第3番を仕上げた頃はすでに健康状態は悪化の一方を辿り、故国ポーランドに残してきた父の訃報が届いたり、サンドとの仲もぎくしゃくしてきて精神的にも不安定な時期だった。
1848年にはパリで二月革命が勃発し、演奏会を開くこともままならなくなった。ショパンは生活の資を稼ぐため、女弟子ジェイン・スターリングの招きでロンドンに赴き、ヴィクトリア女王の御前で演奏したりして半年ばかり滞在したが、この旅行が彼の命取りとなった。そういえばヴェーバーもロンドン滞在で結核が悪化して死んだのだったが、産業革命華やかなりし当時のロンドンの大気汚染の深刻さが窺われる。
そして1849年10月17日の未明、ショパンは還らぬ人となった。
ややこじつけに思われるかもしれないが、ショパンは自分なりの「ソナタ形式」を最後まで模索し続けていたように私には思われる。
彼に続く作曲家は、確かにソナタ形式という構造原理自体にそれほど執着を見せなくなったが、1810年生まれのショパンの世代では、まだ古典的形式をまったく顧みないという段階には至っていないはずである。
ショパンのピアノ曲には、作曲者自身が標題をつけたものは一曲もない。わずかに「幻想ポロネーズ」がそれに近い程度で、その他の「猫のワルツ」「子犬のワルツ」「別れの曲」「黒鍵のエチュード」「革命のエチュード」「雨だれの前奏曲」「軍隊ポロネーズ」「英雄ポロネーズ」「幻想即興曲」などはすべて後人が勝手に命名したタイトルである。ロマン派を特徴づけるひとつの形態である「標題音楽」に、彼はほとんど興味を示さなかった(4曲のバラードが、明記はされていないもののそれぞれポーランド詩人の詩に即して作られた実質上の標題音楽だという説はある。だが、むしろそれらの詩はショパンに作曲のモティベイションを与えただけで、詩の文学的内容を音楽化しようという意図はショパンにはなかったと私は思う)。
彼はやはり、絶対音楽の人だったのである。
確かに彼は「ベートーヴェンのよう」には書かなかった。だが、あくまでも「ショパンのよう」にソナタ形式を書こうとした。その真摯な努力を見過ごしては、ショパンも浮かばれないのではないだろうか。
(2001.5.17.)
|