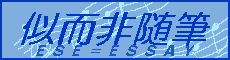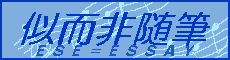|
「絶対音感」という本がベストセラーになったのはそんなに古い話ではない。私はその本を読んでいないので内容の論評はできないが、一時期、
──うちの子に絶対音感をつけさせるにはどうしたらいいでしょうか。
というような親がいろいろと騒がしかったのは憶えている。確か「古畑任三郎」にも、絶対音感を持つ指揮者が登場した話があった。最近はだいぶ騒ぎも下火になってきたようだが、まだ絶対音感というものを何かすごいこと、特別な才能のように思っている人は少なくないのではあるまいか。
「絶対」という字面がものものしいので、そんな気がしてしまうのだが、この「絶対」は「相対」の対語である。ニュアンスとして近いのは数学の「絶対値」などだろうか。絶対値という言葉にはそんな大層な意味はなく、数直線とか複素平面などでゼロ点からの距離を表すだけの術語だ。実数だけを考えるならば、プラスマイナスの符号を取り除いた数と考えればよく、実にもってなんといういことはない概念である。
「絶対音感」というのも、単に、楽器などの装置の助けを借りずに、聴覚だけで音の高さが判別できる能力のことであって、統計をとったわけではないが、多分人間が10人居ればそのうち3、4人くらいは最初から備えていると予想される。この程度の割合で存在するのであれば、少しも特別な能力とは言えない。
もちろん、その判別の精度には個人差があり、訓練によって精度を高めることも可能だ。半音の100分の1程度の音程差でも聞き分けられる人も居れば、半音違っていてもわからない人だって居るわけだが、例えば時報の「ピッピッピッ、ポーン」という音がラだとわかる人であれば、絶対音感を持っていると称してもまったく差し支えない。
絶対音感とは本来この程度のものなのだが、なんだかすごいなあと思われてしまったのは、いわゆる噪音(そうおん……読み方は同じだが「騒音」とは全く別)、例えば手を叩いた時の音とか列車が通過する時の音など、一般には音程がないとされている音の音程を判別してしまう能力を持つ人についての報告があったからだろう。
コップが割れた時の音がシ♭だとか、ノックの音がレ♯だとか言われれば、それは驚くに違いない。
しかし、よく考えればこれも、精度の問題に過ぎない。噪音であっても、高い音低い音という判別はたいていの人がつくであろう。クルマが目の前を通り過ぎると、ドップラー効果で急にエンジン音が低くなる。それがわからない人はあんまり居ないだろう。その精度を上げてゆけば、音程として聞き取ることも無理な話ではない。
戦争中に、飛んでくる敵機のエンジン音を聞き分けて防空に役立てるという作戦が考えられ、絶対音感の養成に力が入れられたことがある。例えばB29のエンジン音ならミ♭、グラマン機ならソ、みたいなことがあらかじめわかれば対空砲火も効果的におこなえるというわけだ。音楽学校の学生などがかり出されて大変だったそうだが、これなどはまさに噪音に音程を求める試みであった。もちろんあとで述べるように、音楽をやる上で絶対音感は必須条件ではないし、音楽家が他の人々より素質的に絶対音感を持っているというわけでもないから、この試みはさっぱり成果が上がらずに終わった。
噪音も楽音も、音である以上空気の振動であることに変わりはない。どこが違うかというと、楽音というのは音波の位相が揃っているのである。いわばレーザー光線の音波ヴァージョンが楽音なのだ。
音楽に用いられる音のうち、噪音の代表は例えば太鼓の音であろう。ところが太鼓の中でも、鍋太鼓(ケトルドラム)と呼ばれるティンパニには音程がある。本当は普通の太鼓にだって音程があるのだがわかりづらいのは事実だ。ティンパニに限って音程がわかりやすいのは、あの独特の半球形(つまり鍋型)の形状に秘密がある。底を半球形にすることで、発生した振動を均等に反射させ、音波の位相を揃えているのだ。凹面鏡で太陽光を集めて焦点を作るのに似ている。
波の位相が揃っているというのは、つまり周波数が一定しているということになる。われわれの耳は音波の周波数を「音程」として認識する仕組みになっている。ちなみに「音の大きさ」は音波の振幅に、「音色」は音波の波形に相当する。噪音は一般的に、周波数も振幅も波形も不安定だ。音程としてなかなか認識できないのは無理のないことと言える。
しかし、不安定とは言え、振幅の大きい周波数領域というのは存在する。小太鼓より大太鼓の方が低い音が出ているとわかるのはそのためである。小太鼓は周波数の高い領域で振幅が大きく、大太鼓は低い領域で振幅が大きくなるわけだ。ただ、位相が揃っていないため、それはある幅の中に連続的に拡がってしまっている。
現代音楽にはトーン・クラスターという技法がある。日本語で言うと「密集音」で、ある音程に含まれる音をすべて鳴らすことを意味する。最初はピアノ曲で使い始められ、まさに「打楽器的効果」を得る手段と考えられた。ただ、ピアノではどうあがいても半音より狭い音程を鳴らすことはできないから、実際には擬似密集音と言うべきで、音波のスペクトルを測定すれば、半音ずつの音程差に相当する周波数にとびとびにピークがある形になるはずである。弦楽合奏などならもっと細かい音程差を作ることができ、ペンデレツキの「広島の犠牲者に捧げる哀歌」などの有名な例に見られるような、トーン・クラスターの効果的な使い方も開発された。とはいえやはり有限の人数が異なった音程を出すだけのことであるから、連続にはほど遠い。
しかしながら、ピアノのクラスターのように事実上はごく非連続的な密集にせよ、弦楽器によるクラスターにせよ、ある程度の「噪音的効果」は出る。古典的な感覚の人には、クラスターは噪音であるばかりか「騒音」にも聞こえるかもしれない。実際の噪音というのは、このトーン・クラスターをさらに塗りつぶして、連続的なスペクトルにしてしまったものと考えればよい。
その連続したスペクトルのうち、比較的強い部分を判別し、それを音程として呼ぶ……噪音の音程を判定できる「絶対音感」とは、要するにそういうことなのである。
実は、この種の絶対音感も、ある程度は訓練でつけることができる。楽音を絶対音で判別できる人ならそんなに難しくない。例えば机を叩いてみる。机の構造によって、叩く場所によって音の高さが違うかもしれないから、そういう違う高さがする場所を何度も叩き較べる。しばらくやっていれば、だんだんそれぞれの音に音程があるように聞こえてくるはずだ。同じ音色で聴き較べてみるというのがミソで、馴れてくれば音程の判断も速くなるし、わざわざ聴き較べなくてもわかるようになってくる。
私でもそのくらいならできるが、だからと言って、身の回りの物音が全部音程を持った楽音のように聞こえてかなわない、などということにはなっていない。注意を集中すればなんとかわかる、程度で、噪音というのはそもそもそういうものだ。もし全部楽音に聞こえるなんて言う人が居たとしたら、相当大げさに言っているか、さもなければ聴覚異常者であって、とてもうらやむような能力とは思えない。
私は作曲家だから、頭の中でイメージした音を、楽器ないし声で発せられるように楽譜化しなければならない。音楽において楽譜というのは必須のものではなく、楽譜なんか無くても音楽はできるが、その場合でも他人に伝えようとすれば、なんらかの手段で実際の音を表現してみせる必要がある。
こういう営みにおいては、絶対音感があることは一応便利である。イメージした音の高さを、いちいちピアノなどで確認しながら楽譜を書かなければならないとしたら、ずいぶん効率が悪いだろう。
逆に、楽譜を見ただけで実際に鳴る音をイメージできるというメリットもある。全く初見の曲でも、現実に音を出してみなくとも大体のイメージがつかめるというのは、練習効率の上から見てかなり有利だろう。
ソルフェージュというのは、そういうことが自然にできるようになるためのトレーニングである。与えられた楽譜を、無伴奏で声に出して歌ってみる視唱。そして与えられた旋律を音符に書き取る聴音。このふたつがソルフェージュの二本柱だ。言い換えれば、絶対音感養成トレーニングと言ってもよい。
本来はそうなのだが、現場では視唱を始める前に、最初の音なり、主和音なりを楽器で鳴らすことが多い。聴音の前にも、たいていは主和音を鳴らす。そういうことが一切なしで視唱や聴音ができればこれは絶対音感ということになるが、主和音を鳴らすことで、いわば定点を与え、その定点からの音程差で音の高さをつかんでゆく、いわば相対音感を併用するのが普通だ。
作曲する時には相対音感だけでは効率が悪いけれども、演奏することにかけては相対音感の方が大切な場合がある。とりわけ、弦楽器や声楽のように、音程の微調整を自力でやらなければならない時には、精度の高い相対音感が必要になり、むしろ精度の高い絶対音感は邪魔になることさえあるのである。
先日、ソルフェージュを教えている生徒に、嬰ヘ長調の聴音課題をやらせてみた。嬰ヘ長調というのは♯が6つもつく調性で、つまりほとんどの音に♯がついてしまっている。ピアノの黒鍵はオクターブに5つしかないから、6つのうちひとつは、♯がついても(つまり半音上がっても)黒鍵にならない。ミの音がそれである。
ミに♯がつくと、半音上がって、ファと同じ音になる。厳密に言えばちょっと違うのだが、とにかくピアノの鍵盤上では同じ音で、いわゆる異名同音だ。
その生徒は絶対音感がある子であったのだが、予想通りと言うか、ミのあたりで混乱が見られた。つまり彼女は、ミ♯がどうしてもファに聞こえてしまうのである。それでついついファの位置に音符を書いてしまい、そのあとの音階をことごとくひとつ高い音で書いてしまっていた。旋律聴音の場合、音の動きが音階になっていると、普通はひとつひとつの音を聞き分けるよりも、音階全体として認識することが多い。だから音階が始まる最初の音を間違えると、途中で修正が利かず、全部間違ってしまうのである。
この結果は、絶対音感というものの弊害を端的に表している。
嬰ヘ長調のミ♯という音は、導音という大事な役割を持った音だ。これがファでは導音にならない。異名同音なのだから同じことではないかと思われるかもしれないが、いわゆる機能調性音楽においては、ミ♯とファとは役割がまるで違ってくるのである。
単なる絶対音感では、この区別ができない。ファの音はファとして使われる方が圧倒的に多く、異名同音的にミ♯とされることは少ないため、単なる絶対音感の持ち主は、この音はファであるとして記憶してしまう。嬰ヘ長調で使われようが、ファはファであって、ミ♯とは認識できないのだ。
音楽をやる者にとって、これは欠陥としか言いようがない。
調性感覚(もしくは和声感覚)を欠いた絶対音感などは、音楽をやる上では百害あって一利なしなのである。
さらに、実は、ソならソという音は、ひとつだけではない。
ドミソという和音のソと、シレソという和音のソは、厳密に言うと高さが違うのである。
ピアノのような、いわゆる平均律に調律されている楽器であればもちろん同じ音なのだが、平均律というのはオクターブを機械的に12等分した調律であり、和音にすると若干濁りが発生する。
美しく響かせるのを最優先させた調律法を純正律という。
ドとソとの音程は完全5度と言い、周波数にして2:3というきわめて整然とした比率になり、他の音程もこれを基礎にして調整される大事な音程なのだが、ピアノに使われている平均律では実は2%ほど狭くなっている。つまり周波数の比率で言えば2:2.98くらいになり、その分濁っていることになる。
もっとも基礎的であるべき完全5度すらこんなていたらくなのだから、他の音程は推して知るべし。
われわれはピアノの音に馴れてしまっているからそんなに違和感を感じないけれども、たとえば一流の合唱団がピアノ伴奏付きの曲を歌っていたりすると、妙にピアノが浮いて聞こえてしまうことが少なくない。合唱は純正律で演奏し、ピアノは平均律のままだからこういうことになってしまうのだ。うまい合唱団は無伴奏の曲を演奏することが多いが、これは「無伴奏でも歌える」からやっているのではなく、うまくなればなるほどピアノの音とのピッチの乖離が目立ってきてしまうからである。
純正律はきわめて美しく響くが、その代わり音程を不断に微調整しなければならない大変な調律法である。鍵盤楽器で純正律を出そうとして純正律オルガンなるものが作られたが、オクターブに普通のピアノやオルガンの倍である24個の鍵盤を備え、しかもそれをレジスター操作で2通りに使い分ける必要があるので実際には48個の音を使うことになる。まともに演奏できる人は世界でも数人しかいないそうだ。
要するに簡単に言えば、上に挙げたように、ドミソのソとシレソのソを別の鍵盤で弾かなければならない、ということである。
こういう微調整を怠るとどうなるか、炎のコンティヌオさんが具体的に例証しておられるので、興味のあるかたはご参照下さい。
ともあれ純正律は鍵盤楽器では不経済で困難な調律法なのだが、弦楽器や声楽などでは当然意識しなければならない。自力でピッチを微調整できる楽器(人声も楽器の一種として)の奏者は、常に自分の出している音が全体の和声の中でどういう役割を占めているのかを認識し、細かく音の出し方を変えてゆかなければならないのである。ロングトーンだからと言ってぼーっと音を伸ばしていると、収拾がつかなくなってしまうことさえあるのだ。
さて、精度の高い絶対音感を持ちながら調性感覚、和声感覚に欠ける奏者がアンサンブルに混じると、この微調整がうまくゆかない。むしろ精度が高いほど困ったことになるとさえ言える。
冒頭に挙げた、半音の100分の1という微音程まで区別してしまう人の場合で考えてみよう。完全5度音程は純正律と平均律で2%ほども差があると書いたが、これは半音の7分の1くらいの音程差である。つまり、同じ音とされるものでもそのくらいの揺らぎがあるのが普通なのだ。ところが、半音の7分の1も揺らいでしまっては、この人にとってはまるで別の音に聞こえてしまうはずである。この人がソならソと思っている音からそれほどかけ離れてしまっては、気持ちが悪くてたまらないだろう。逆にこの人が自分の音程に固執するならば、アンサンブルは実にぎくしゃくとした稚拙なものになってしまうだろう。
もちろん、精度の高い絶対音感を持っていても、すぐれた和声感覚を併せて持っているならば問題はない。
つまり、音楽という営みに関する限り、絶対音感は調性感覚や和声感覚に従属するべきものだということがわかるであろう。逆に和声感覚がすぐれていれば、絶対音感など無くても済む。むしろ相対音感の方が大事である。
絶対音感の精度と音楽的能力は、ほぼ無関係と言い切って良いと思う。
前半で書いた、噪音から音程を抽出する能力に至っては何をかいわんやである。
さて、それでもお子さんに絶対音感を身につけさせたいと思われるだろうか?
(2002.10.15.)
|