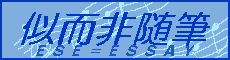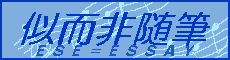|
ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスなどといった大物が一生独身であったためか、作曲家は独身者が多いとか、恋が結ばれない方がいい曲が書けるとか、そんなことを思っている人が結構数多い。
もちろん、そんなことはないので、圧倒多数の作曲家は妻帯しているし、恋や結婚と作品の質とが関係しているという根拠もない。
昔は音楽家も世襲制であることが多かったから、もちろん子供を作る必要があった。かの大バッハは2回の結婚で、実に20人の子供を作っている。毎週1曲ずつのカンタータを作曲するなどという超人的な忙しさの中で、よくもまあそんなに作っている閑があったと感心する。さすがに「大」バッハの名は伊達ではないが、この絶倫なる巨匠につきあって13人も産んだ後妻のアンナ・マグダレーナもただものではない。
ヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)の結婚が不幸だったことはよく知られている。
もともと意中のひとだった娘が、ハイドンが躊躇しているうちに修道院に入ってしまい、それで失恋したというのも情けないが、その娘の親から、
「まあ、同じようなものですよ」
と、売れ残っていた姉娘を押しつけられたというのだからさらに情けない。
そしてこの妻マリア・アンナ・アロイジアは、音楽史上最悪の悪妻として知られるようになったのである。あの温厚篤実な「師父」ハイドンが、
「あの女は、自分の夫が音楽家だろうが靴屋だろうが、どうだっていいんだ」
とぼやいたほどで、年柄年中がみがみ怒鳴りつけられ、罵られ、いびりぬかれたのであった。
ハイドンはよほどたまりかねたのか、「イヤな女房」というカノン(輪唱曲)まで書いている。
しかし、このエピソードは単に笑い話として片づけられないものがある。早い話がマリア・アンナにしても、それこそ靴屋の女房になっていれば、それほどの悪妻にはなっていなかったかもしれない。本来かつら屋の娘に過ぎない彼女は、音楽にも興味がなかったし、音楽家の生活の不規則さや不安定さに耐えられなかったのだろう。
一説によると、ハイドン先生のこの不幸な結婚をまのあたりにした弟子のベートーヴェンは、すっかり怖じ気をふるってしまって、一生結婚などするものかと決意したというのだが、それはどうも怪しい。ベートーヴェンはちゃんと人並みに恋もしているし、プロポーズめいたこともしているからである。
ベートーヴェンが結婚できなかったのは、要するに「ムリめの女」ばかり狙ったからではないかと思われる。
例えば前回名前を出したテレーゼ・ブルンズヴィック伯爵令嬢などがいい例で、彼女に贈ったピアノソナタ第24番「テレーゼ」は、ほとんど聴く方が恥ずかしくなるくらい甘ったるい憧れに満ちている。またあの「エリーゼのために」も、もともとは「テレーゼのために」であったという説が有力である。
テレーゼ以外でも、ベートーヴェンが惚れるのはたいてい貴族の令嬢であって、そもそも身分違いの恋ばかりなのであった。ルードヴィヒ・ヴァンというのが彼の名だが、この「ヴァン」というのは、画家のヴィンセント・「ヴァン」・ゴッホ同様、オランダ系のありふれたミドルネームであるに過ぎず、もちろん貴族をあらわす「フォン」とはなんの関係もない。しかし、一時期彼の「ヴァン」が「フォン」と間違えられたことがあり、ベートーヴェンは訂正もせずに大きな顔をしていた。あとで間違いと判明したとき、大変気まずかったらしい。
これで見ても、ベートーヴェンは結構貴族コンプレックスの強い男であったと思われる。自分の同階級の女など眼中になかったのではないか。
「愛の前に、身分や階級の差なんて関係ない」
というのは現代の考え方であって、当時のヨーロッパではそんなことを考える者はいなかった。
ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)の妻はご存じコンスタンツェで、これも音楽史上の悪妻とされている。その妹の方が本命であったという点、ハイドンのケースとよく似ているが、しかしコンスタンツェは本人も歌手であって、マリア・アンナのようなことにはならなかった。
そして大違いなのは、モーツァルト自身はこの妻をすこぶる愛していたらしいということだ。なにしろ死の年にさえ三男が生まれている。
確かにコンスタンツェはあまり生活能力もなく、夫の死後遺稿を二束三文で叩き売ってしまったり(生活のため)、葬儀にも出席しなかった(病気のため)など、決して褒められた女性ではないが、彼女を悪妻と呼ぶのはある意味では余計なお世話かもしれない。なんとモーツァルトは、彼女のことを、
「とてもやりくり上手な働き者の女房」
と評しているのである。本人がそう思っているものを、はたからあれこれ言うのは、まず馬に蹴られて死んでしまってしかるべき振る舞いではあるまいか。
いろんな作曲家について、ざっと瞥見してみようと思ったのだが、なかなか面白い話題なのでつい長くなってしまった。よって、この項は次回に続くということにいたします。
|