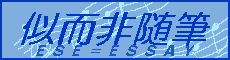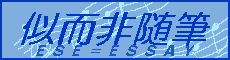|
フランツ・シューベルト(1797-1828)がベートーヴェンに大変心酔していたのはよく知られている。まさか女性の好みまでベートーヴェンに倣ったとは思われないのだが、シューベルトもやはり「ムリめ」好みであったようだ。
19歳の頃に、音楽の家庭教師として教えたエステルハージ伯爵の令嬢マリー(当時16歳)に惚れたのであったが、当然ながら結ばれようもなかった。なにしろシューベルトは、31年の生涯のほとんどを兄や友人の家に居候して廻っていたような男で、生活能力はゼロに近かった。たとえ身分のことがなくても、こんな男に娘を嫁がせたがる親はいないだろう。
この失恋はよほどこたえたのか、シューベルトはその後の短い後半生において、恋愛をした形跡がない。安い娼婦と寝た(金がないため)ばかりで、気の毒にも梅毒をうつされて早世した。
ドイツロマン主義音楽の祖として、シューベルトと並び称される、カール・マリア・フォン・ヴェーバー(1786-1826)は、モーツァルトの妻コンスタンツェの従弟にあたる。モーツァルトも愛妻家であったが、ヴェーバーはそれに輪をかけていて、3つ歳下の妻カロリーネを溺愛した。愛妻家の作曲家を挙げれば、まずこのヴェーバーと、英国のエドワード・エルガー(1857-1934)が東西の横綱格であろう。奇しくも、このふたりの妻は同じ名前である(エルガー夫人の名はキャロライン・アリスで、キャロラインをドイツ語読みすればカロリーネとなる)。エルガーは妻の死後、ほとんど作曲をしなくなってしまったほどである。
なお、ヴェーバーの有名な「舞踏会への招待」は、傍らのカロリーネにひとつひとつ物語りながら作曲したという伝説がある。
愛妻といえば、ロベルト・シューマン(1810-56)の名を忘れるわけにはゆかない。クララ・ヴィークとの長い恋は、音楽史上屈指のロマンスとして、特にピアノを学ぶ女の子たちの憧れの的である。
「娘にこれ以上近づいたら、奴を射殺してやる」
とまで放言したクララの父親の頑固親父ぶりも、このロマンスに彩りを添えている。
あまたの困難にめげず、クララへの愛を貫き通し、ついに結婚に漕ぎつけたシューマン。あんな大音楽家にそこまで想われてみたいというのは、女性にとっては当然の願望であろう。
もっとも、私の見るところ、この話は少々割り引いた方がいいようである。
まず、ずっと想い続けたのはクララの方であって、シューマンは結構、浮気とは言えないまでも、他の女に目移りしているのである。エルネスティーネ・フォン・フリッケン、クララ・ノヴェッロ、ロヴェーナ・アンナ・ライドローなど、いろんな女の名前が残っている。
ヴィーク氏の頑強な反対に、もともとむら気なところのあるシューマンは、正直言って疲れたのだろう。
「クララなんか、もうどうでもいいや」
と思ったことがあっても不思議ではない。
曲がりなりにも5年間の困難な恋を貫いたのは、むしろクララの方に少しも迷いがなかったからだったろう。クララという女性は決して良家のお嬢さま、深窓の令嬢といったタイプの人ではなく、どちらかというとおきゃんな、鉄火肌のところがあったらしい。彼女は世界最初の天才女流ピアニストであると言われる。「最初の天才女流云々」と呼ばれる女性がどんなキャラクターであるかは、他のいくつかの例を考えてみれば大体見当がつく。
かくして熱愛の末結婚したふたりであったが、14年で破綻する。シューマンが投身自殺を図り、その後精神病院に収容されてしまったのだ。精神分裂症と診断されたからだが、「最初の天才女流ピアニストの夫」となってしまったシューマンの悲鳴が聞こえるような気がするのは私だけであろうか?
こうしてみると、ふたりとも「最高の恋人」ではあっても、「最高の夫」「最高の妻」であったかどうかは疑わしい。もちろん、家庭生活は円満であったと伝えられるが……。
シューマンの弟子であったヨハネス・ブラームス(1833-97)は、このクララを深く愛したが、恩師の未亡人に求婚するわけにもゆかず、愛の苦悩に身を焦がしつつ、一生独身で過ごした、とたいていの伝記に書いてある。これはまた、せつないほどの純愛ではあるまいか。かつて私があるピアニストに失恋し、彼女が他の男と結婚してしまった時、あろうことか私をブラームスに、彼女をクララになぞらえ、
「君は一生彼女への純愛を貫き通したまえ。そうすればきっと、ブラームスのような曲が書けるよ」
と、いらんお節介を焼いてくれた友人が居た。この友人は、もちろんブラームス純愛説を信じていたわけである。
が、これも真相は違うようだ。
ブラームスは娼館の立ち並ぶような街で生まれ育ったため、現実の女性にほとんど興味を持てなくなってしまったらしいのである。今なら2次元美少女オタクにでもなっていたかもしれない。クララの方が15歳も歳上だというのはまあいいとしても、どうやらクララへの感情は「敬愛」であって、異性としての愛ではなかったように思われる。読者諸氏はどうお考えであろうか。
この項、まだ続きます。お楽しみに。
|