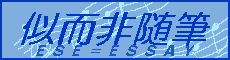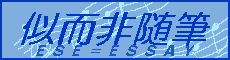|
フリデリック・ショパン(1810-49)の異性関係というと、即座に女流詩人ジョルジュ・サンド(1804-76)の名が浮かんでくる。
ジョルジュ・サンドといえば19世紀前半という時代にパリの街をパンタロンをはいて闊歩し、詩人ミュッセとも浮き名を流した女傑である。今に残る肖像写真を見ても、意志の強そうな、一筋縄ではいかない感じのオバチャンではある。
一方、一般的なショパンのイメージは、結核に冒され、風がそよいでも倒れそうな、線の細い、神経質な美男子というところ。6歳上の女丈夫とのロマンス、となると、いやが上にもショパンは弱々しいやさ男に見えてくる。サンドの母性的な庇護のもとにようやく生きていられたかのようである。
しかし、ショパンのキャラクターについては、実際には次のような証言が伝えられている。
★ショパンはマンガが上手だった。
★ショパンは漫談の名手で、彼がしゃべり出すと満座は笑いの渦に巻き込まれた。
★ショパンはポーランド独立運動に身を投じていた闘士であり、当局のブラックリストにも載っていた。
どうも、なよなよした腺病質の青年というイメージとは違うようである。
実際、ショパンのピアノ曲の中には、相当な体力を要するものも多い。協奏曲は言うに及ばず、ソナタにしても、ポロネーズ、スケルツォ、バラードなど、弾き終わるとへとへとになる。とても、線の細い男の作った曲とは思えない。
実はショパンはすこぶる健康な青年であって、その健康にものを言わせて無理をしすぎたために、結核にかかってしまったのである。
サンドとの間でも、ただ優しく護られていただけではなかったようで、時々大喧嘩をしている。「幻想曲」は彼らの喧嘩と仲直りを描いたのだ、とも言われている。
ただし、歳下ということもあってか、大分甘ったれてはいたようで、フェミニズムの元祖たるサンドの思想などを、どの程度理解していたかは疑問だ。サンドが革命運動の同志の男性たちと会うのに、いちいち焼き餅を焼いている。漫談の名手だっただけに、そういう時の皮肉も辛辣なものだったろう。サンドも時折はやりきれなくなったかもしれない。
サンドが前夫デュドヴァン男爵との間に作った子供たちとも、折り合いが悪かったようで、どうも彼らの仲は、マジョルカ島での甘い生活というイメージと裏腹に、かなり波風の多い日常だったのではないかと思われる。
サンドをショパンに引き合わせたのが、フランツ・リスト(1811-86)である。リストは独身を通したが、これは彼の意図ではなかった。彼を色豪と考える人が多いが、不本意ではなかったかと思う。
色豪と考えられる理由はいくつかあるが、なんといってもリストの生涯を彩ったふたりの女性が、いずれも人妻であったことが大きかろう。マリ・ダグー伯爵夫人とカロリーネ・フォン・ザイン・ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人である。夫のある女性を、ふたりもものにして、駆け落ちさせているくらいだから、よほどの豪の者だろうと思われてもやむを得ない。
しかし、このふたりを同時に愛したとでもいうのなら話は別だが、マリとの破局とカロリーネとの出逢いの間には8年のタイムラグがあり、しかもどちらの女性とも、リストは真剣に結婚を考えている。決してちょっとした火遊びのつもりではなかった。
大体人妻というものは、自分の夫に不満が多いものであって、特に政略結婚が多かった当時の貴族の場合は、夫に我慢のならない侯爵夫人や伯爵夫人がごろごろしていただろう。親切で、才能があって、しかも美男子で、ピアノのレッスンともなれば長時間膝を突きあわせる相手によろめいてしまっても不思議はなく、人妻をものにしたのが必ずしもリストの「功績」と言えるかどうか。
リストは何度も出家して修道院に入ろうと考えたほどの男であって、人生に対して不真面目に考える人間でなかったことは確かである。カロリーネと結婚するために、前夫との離婚が認められるよう、必死になって奔走したが力及ばず、それでも決して嫌気がさしたりせずに、彼女を愛し抜いた。死期が近いことを悟ると、穏やかに彼女に別れを告げ、マリとの間の娘コジマ(指揮者でピアニストのハンス・フォン・ビューロー夫人、のち作曲家リヒアルト・ヴァーグナー夫人)のもとで最期を迎えるべく去って行った。
その後ろ姿からは、猟色家どころか、人生を力一杯、真摯に生き抜いた、堂々たる老紳士の印象を受けはしないだろうか。
作曲家の異性関係を探れば、まだまだいろんな話があって面白いのだが、最後に例の男色家チャイコフスキーの場合を取り上げて終わりにしたい。
彼はちゃんと結婚している。37歳の時、もと教え子だったアントニーナ・イヴァーノヴナと一緒になった。
この結婚は、ハイドンの結婚と並ぶ、音楽史上もっとも不幸な結婚と言ってよいかもしれない。18世紀と19世紀の差もあってか、ハイドンのケースよりややこしく、さらに言わせて貰えば、チャイコフスキー本人には満腔の同情を捧げるにしても、どこかドタバタ喜劇めいていて、見ている方は面白い。
何せ、ホモとストーカーの結婚なのである。
アントニーナは、チャイコフスキーの追っかけであって、ほとんど常軌を逸したような手紙を送り続けた。結婚してくれなければ自殺すると脅迫したのである。
チャイコフスキーの方にも弱みがあった。ホモだという噂が広まりつつあり、結婚でもしてみせないことには、容易に打ち消せない状況にあったのだ。今と違い、同性愛は刑事罰の対象となる時代である。
焦ったチャイコフスキーは、ストーカー女の脅迫に乗って、結婚してしまった。
不幸にならない方がおかしいような話ではないか。
ひょっとしたら、一緒に暮らすうちに、女を愛せるようになれるかもしれない、とチャイコフスキーは考えたようだ。
尋常な女であれば、もしかするとそういうことにもなったかもしれない。
ところが、アントニーナはストーカーだけあって、尋常ではなかった。どうもはっきりと異常だったらしい。チャイコフスキーと別居したあと(離婚はしなかった)、彼女は他の男の子供を何人か産むが、ひとりも育てようとせず、孤児院へ送ってしまったのである。
チャイコフスキーは逃げ出し、嫁いだ妹の家にころがりこんだ。この時書かれた交響曲第4番は、何やら解放の喜びに満ちあふれているとしか言いようがない。
アントニーナも変な女ではあったが、要するに、同性愛者が世間体のために結婚などしても、誰も幸せにはなれないという見本のような話である。
|